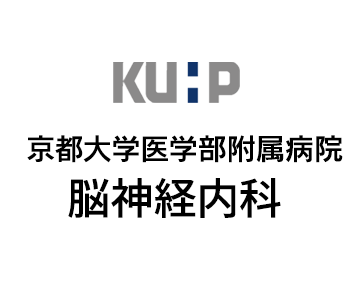研修プログラム
脳神経内科の特徴
脳神経内科は、大脳から脊髄、末梢神経、から筋肉までのシステムに関係する広範囲の疾患を診療します。しびれ感、めまい、頭痛、物忘れ、けいれんなど日常よく遭遇する訴え・症状から、意識障害、急性の呼吸筋麻痺といった重篤な症状までを扱い、正確に診断し適切に治療する力が求められます。主な疾患として、
- てんかん
- 脳卒中
- アルツハイマー病
- パーキンソン病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 多発性硬化症、視神経脊髄炎
- 重症筋無力症
- 脳炎、髄膜炎
- 末梢神経障害
などがあります。さらに、様々な内科疾患、脳神経外科疾患、耳鼻科疾患、眼科疾患、精神科疾患なども神経学的異常をしばしばきたすため、他科患者のコンサルト対応を含めた広い診療能力も求められます。専門性の高い診療能力を身につけるためには、優れた指導者のもとで豊富な症例を経験することが不可欠です。また、慢性疾患中心の病院と救急疾患を扱う病院の両方で研修を行う必要もあります。
週間スケジュール
| 月 | 19:00 | 脳機能てんかんグループカンファレンス(月1) |
|---|---|---|
| 火 | 9:00 | 脳波カンファレンス |
| 13:00 | 病棟カンファレンス・回診 | |
| 水 | 19:00 | 脳波カンファレンス |
| 木 | 8:30 | 教授との教育回診 |
| 金 | 8:30 | パーキンソン病カンファレンス |
| 9:30 | 神経画像カンファレンス | |
| 11:00 | 病棟医長・副医長との経過カンファレンス | |
| 15:00 | 専門領域回診(曜日・時間帯は担当スタッフにより異なる) |
後期研修(卒後3-5年目の内科専攻医)・入局について
京都大学脳神経内科では、”World class care and research”をモットーに、臨床・研究の両面で日本そして世界のリーダーとなる脳神経内科医=Physician-Scientistの育成を目指しています。そのため、充実した後期研修プログラムを提供しています。
京都大学病院脳神経内科での後期研修
京都大学病院の脳神経内科では、各専門領域に精通した専門医が高度な診療を行っており、豊富な症例を経験できます(表1)。
また、症例検討会やカンファレンス(全体での病棟カンファレンス、および脳波、画像、疾患ごとのカンファレンス)に加え、学外の専門家を招いたセミナーも定期的に開催しており、脳神経内科専門医を目指すための最適な環境が整っています(週間スケジュール)。
「脳神経内科研修セミナー」は20年以上継続して開催されており、関連講座・部署のてんかん・運動異常生理学、てんかん診療支援センターと合同で行う「脳波てんかんセミナー」も10年以上開催されています。これらの教育セミナーを通じて、より深い専門知識を習得できます(教育セミナーのページはこちら)。
| (年度) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性疾患 | パーキンソン病、脊髄小脳変性症、ALSなど | 230 | 236 | 205 | 216 | 203 | 150 |
| 機能性疾患 | てんかん、運動異常症 | 142 | 108 | 79 | 102 | 68 | 71 |
| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血など | 123 | 103 | 160 | 178 | 109 | 54 |
| 神経免疫疾患 | 多発性硬化症、ギランバレー症候群など | 69 | 24 | 45 | 36 | 29 | 22 |
| 末梢神経疾患 | ビタミン欠乏性ニューロパチーなど | 46 | 24 | 35 | 37 | 10 | 13 |
| 認知症 | アルツハイマー病、レビー小体型認知症など | 41 | 20 | 34 | 36 | 16 | 38 |
| 感染症・炎症性疾患 | 髄膜炎・脳炎・脳腫瘍 | 6 | 30 | 49 | 32 | 13 | 9 |
| 総数 | 680 | 682 | 608 | 666 | 716 | 654 | |
脳神経疾患の診断トレーニング(3-step diagnosis)
初期研修医・後期研修の内科専攻医に対しては、脳神経疾患の診断において”3-step diagnosis(3段階診断法)”のトレーニングを重視しています。
- 解剖学的診断(anatomical diagnosis)
症状と所見に基づいて病変部位を推定する。 - 病因診断(etiological diagnosis)
発症様式と経過から病態または病院を大きく捉える。 - 臨床診断(clinical diagnosis)
上記の1.と2.に基づいて、最も可能性が高い臨床診断を暫定的に決定し、それに対する鑑別診断をリストアップする。
正確な病歴聴取と神経学的診察(陽性および重要な陰性所見)を行い、3-step diagnosisを実践できることが、脳神経内科専門医になるために最も重要です。さらに、脳MRIなどの各種臨床検査を活用し、診断から治療までの流れを身につけます。
後期研修での実践的トレーニング
後期研修では、以下の研修・トレーニングを日々行います。
病棟担当医としての診療
- 3人体制の主治医団の担当医(期間途中から中間医)として、幅広い神経疾患の診断・治療に携わります。
- 週1回の病棟カンファレンスでは、3-step diagnosisに基づいて新入院患者のプレゼンテーションを行います。
- 診断・治療に特に難渋する症例は、クリニカルカンファレンスにて文献考察を交えながら発表し、チーム医療の実戦を学びます。
神経救急患者対応
- 平日日中の救急当番、および夜間・土日日中の当直では、救急外来あるいは他科患者コンサルト対応など、神経救急の研修を行います。
- 意識障害の鑑別、脳卒中・てんかんなどの診断、初期治療について実践的に学びます。
- スタッフ医師のバックアップ体制が整っており、一人で判断を迫られることはありません。
電気生理学的検査の習得
- 入院患者の神経伝導検査・筋電図、誘発電位を指導医のもとで実施し、レポート作成まで行います。
- 担当患者の脳波を指導医と共に判読し、脳波カンファレンスでの検討にも参加します。
頸動脈エコーの習得
- 脳梗塞の病型診断や治療法決定に直結する頸動脈の評価法を習得します。
神経画像診断力の習得
- 週1回の神経画像カンファレンスでは、放射線診断科神経グループ医師と問題症例を検討します。
パーキンソン病デバイス補助療法
- 脳深部刺激療法(DBS)、L-dopa持続経腸投与療法、持続皮下投与療法などのデバイス補助療法を入院担当医として経験します。
- パーキンソン病カンファレンスで治療適応の検討にも関わります。
学会発表・論文執筆
- 診断や治療に関して特に重要な症例は、スタッフ医師の指導のもと学会発表・論文執筆を積極的に行います。
京都大学脳神経内科関連病院での後期研修
京都大学脳神経内科には30近くの研修協力関連病院(※)があり、いずれも地域の第一線病院です。これらの病院の脳神経内科では、経験豊富な指導者のもとで研修を行うことができます。
京大病院および研修協力関連病院での後期研修(卒後3-5年目の内科専攻医)プログラムをもとに、大学と関連病院あるいは関連病院間の相互乗り入れの研修を基本とし、慢性疾患から救急疾患までバランスのとれた臨床能力を養うことを目的としています。
京大脳神経内科の関連病院では、それぞれの施設が、急性期脳卒中、パーキンソン病、認知症、多発性硬化症など、重要なcommon diseaseを数多く診療し、それぞれの特色を活かした医療を提供しています。そのため、研修を通じて実戦的な診療能力を磨くことができます。
これまで京大脳神経内科およびその関連病院で研修した医師ほぼ全員が日本神経学会認定の神経内科専門医の資格を取得しており、今後も後期研修修了者は全員神経内科専門医試験に合格してもらう方針です。初代亀山正邦教授、2代目木村淳教授、3代目柴崎浩教授、4代目髙橋良輔教授のもと、昭和56年の創設以来40年以上の間に京大脳神経内科の同門会は500名を超える専門医が所属する組織に発展し、脳神経内科専門医の質・量ともに日本有数の集団になっています。また、てんかん専門医や脳卒中専門医などのsubspeciality資格の取得を目指す方に向けて、研修の細かい配慮・サポートも行います(表3)。
表3:京大脳神経内科での後期研修により取得可能な専門医
| 専門医資格 | 認定学会 |
|---|---|
| 神経内科専門医・総合内科専門医 | 日本神経学会 |
| 総合内科専門医 | 日本内科学会 |
| 脳卒中学会専門医 | 日本脳卒中学会 |
| てんかん専門医 | 日本てんかん学会 |
| 日本臨床神経生理学会専門医 (脳波分野と筋電図・神経伝導分野) | 日本臨床神経生理学会 |
| 臨床遺伝専門医 | 日本遺伝カウンセリング学会 |
| 認知症学会専門医 | 日本認知症学会 |
| 老年医学会老年病専門医 | 日本老年医学会 |
後期研修から未来へ
神経内科専門医の取得を目指す若手医師には、目の前の患者一人ひとりを大切にし、丁寧な診療を行うことが求められます。その過程で臨床能力を高め、医師として人として成長することが、将来大学院で「治る脳神経内科」をさらに目指した研究活動へと繋がります。
関連リンク
初期研修(卒後1-2年目)について
かつて脳神経内科の疾患は、「診断はできても治療法がない、あるいは限られる」時代が長く続いていました。しかし近年、臨床・研究の進歩により、次のような新しい治療法が確立されつつあります。
- パーキンソン病に対するiPS細胞移植
- 各種神経疾患に対するニューロモデュレーション治療
- てんかん外科治療
- 超急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法・血管内治療
- アルツハイマー型認知症に対する抗体療法
- 神経免疫疾患に対する疾患修飾薬
これらの進歩により、「治る脳神経内科」の時代に移行しつつあります。しかしながら、脳神経内科の領域は奥深く、今なお未知の部分が多く、その探究は「人間そのものを深く理解すること」にも繋がります。これは自然科学全体の根源的な目的でもあります。さらなる発展が期待される脳神経内科の世界で、ぜひ一緒に学び、働きませんか?
脳神経内科で初期研修を行うメリット
脳神経内科で初期研修を通じて、以下のスキルを身につけることができます。
- 自信を持って、神経学的所見の診察を行えるようになる
- 腰椎穿刺(ルンバール)を習得できる
- 将来どの診療科に進んでも、適切に脳神経内科医に相談できるようになる
さらに希望に応じて、神経伝導検査・筋電図検査、脳波、頸動脈エコー、脳深部刺激療法(DBS)など、より専門的な診療にも関わることができます。
学会発表や論文執筆にも挑戦!
診断や治療において特に重要な症例については、研修医の先生にも積極的に学会発表していただきます。(学会賞受賞や論文発表も多数あります!)
関連リンク
連絡先
ご興味のある方は、遠慮なく以下よりメールにてご連絡ください!
病院見学(1日でカンファレンス・回診への参加と研究室見学)も随時受け付けています!
京都大学 脳神経内科 neuroofc@kuhp.kyoto-u.ac.jp