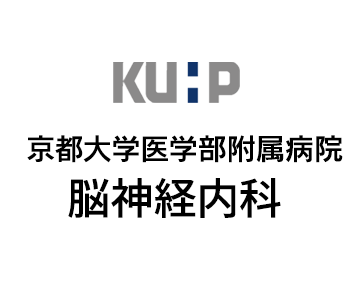神経免疫グループ
研究紹介
ミクログリアと中枢神経系の慢性炎症病態
中枢神経系(脳・脊髄)の自己免疫疾患として、主に多発性硬化症(MS)、視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)、MOG抗体関連疾患(MOGAD)等が知られる。MSやNMOSDに対して多くの治療薬が開発され、その予後は大きく改善している。しかしながら、特にMSにおいては、脳内の慢性炎症が問題として残っている。慢性炎症は、再発によらない進行(PIRA: progression independent of relapse activity)の一因であり、PIRAが長期予後不良に直結することが知られている。また、慢性炎症に対しては、従来の治療薬の効果が期待しづらく、アンメットニーズと考えられる。一方、脳内の慢性炎症は、アルツハイマー型認知症(AD)等、他の中枢神経系難治性疾患の病態とも密接に関わっている。従って、慢性炎症の制御は、多くの難治性病態解決の鍵を握っていると考えられる。
脳内慢性炎症には様々な細胞が関与しているが、なかでもミクログリアが重要視されている。ミクログリアは脳内環境の変化に応じて大きく形質を変え、MSやADのリスク遺伝子解析からもその重要性が支持される。MSやADの病理学的検討からは、ミクログリアが慢性炎症病態のハブとなり、周囲の細胞と相互作用することによって炎症を持続させることが示唆されている。ミクログリアは、炎症に寄与する以外にも様々な機能を有しており、治療開発のためにそれらの精密制御が求められている。
当グループの木村は、これまでに免疫チェックポイント分子Tim-3の解析を通して、ミクログリアの制御機構の一端の解明に成功している(Nature 2025、プレスリリース)。現在は、ミクログリアの制御機構の解析を、より詳細かつ網羅的に行っている。これまでのCRISPR screening等の経験(Nature 2024)も解析に応用しており、新規クラスの治療開発を最終的な目標として研究を進めている。また、濱谷・藤田は、免疫細胞生物学教室において、iPS細胞由来ミクログリアを用いて難治性遺伝性疾患であるALSP(adult-onset leukoencephalopathy with neuroaxonal spheroids and pigmented glia)の病態解明・治療開発研究を進めている(Neurobiology of Disease 2020)。
T細胞・B細胞と自己免疫病態
T細胞・B細胞といったリンパ球は、自己抗原を標的とした自己免疫疾患の病態に深く関与している。MSやNMOSDにおいても、T細胞の動態を調整したり、B細胞を除去する薬剤によって再発を抑制できる。こうしたリンパ球は末梢から中枢神経系に浸潤するため、末梢側での制御を念頭においた治療開発が進められてきた。一方で、中枢神経系に浸潤した後にとどまっているリンパ球(組織常在性リンパ球)が、上記でふれた慢性炎症に寄与することが示唆されている。具体的な例を挙げると、MSでは、脳表にリンパ濾胞様構造をしばしば認め、さらに脳実質では浸潤リンパ球とミクログリアとの相互作用が想定され、臨床的な病態進行と関連している。このような側面において、組織常在性リンパ球の重要性が認識されている。当グループでは、こうしたresident memory様のCD8 T細胞頻度が、MS患者の髄液で上昇していることを見出した(Neurology N2 2024)。錦織はNMOSD患者の髄液においても、CD4 T細胞とCD21lo B細胞がともにresident memory様のマーカーを発現し病態に寄与することを明らかにしている(Brain 2025; 免疫細胞生物学教室との共同研究)。また、興味深いことに、ADやパーキンソン病においても、髄液中のresident memory様CD8 T細胞頻度の上昇を認めた。組織常在性リンパ球を起点とした慢性炎症が、中枢神経系の自己免疫疾患と一部の変性疾患で共通している可能性を考えている。
個々の疾患におけるリンパ球の特異的な異常についても研究を進めている。リンパ球は周囲の環境因子によってその分化・性質が調整されており、木村、濱谷はMS病態における血中エクソソームやミエリン糖脂質の関与を明らかにしてきた(Nature Communications 2018; Molecular Neurobiology 2022)。こうしたリンパ球の解析を通して、疾患治療の個別化(テーラーメイド医療)につながる可能性もあり、実際に木村は、血中のTh1細胞頻度によって、MS患者の血液浄化療法の有効性を予測できることを見出している(Annals of Neurology 2021)。最新の解析手法を応用し、リンパ球を含めた自己免疫機構を詳細に解析して、得られた知見を臨床現場へ還元することを目標として研究を進めている。
神経免疫グループ メンバー
木村公俊、錦織隆成、平田真也*、堀晃暢*、田中大暉*
髙田真基・篠藤祐也・藤田理奈(免疫細胞生物学教室併任)
濱谷美緒(ASHBi)
共同研究:近藤誉之(関西医科大学)
*大学院生
業績(神経免疫グループメンバーが関わったもの)
Nature. doi: 10.1038/s41586-025-08852-z. 2025. プレスリリース. Brain. doi: 10.1093/brain/awaf086. 2025. Neural Regen Res. 20(11):3227-3228. 2025. Eye Brain. 16:65-73. 2024. Nature. 635(8038):444-452. 2024. Immunol Med. 47(3):151-165. 2024. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 11(1):e200172. 2024. Neural Regen Res. 18(9):1950-1951. 2023. Mol Neurobiol. 59(9):5276-5283. 2022. Front Neurol. 13:1012857. 2022. Front Immunol. 13:1048428. 2022. Annals of Neurology. 90(4):595-611. 2021. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 8(2):e945. 2021. Front Neurol. 12:749406. 2021. Brain Nerve. 73(5):450-457. 2021. Clinical and Experimental Neuroimmunology. 11(3): 148-155. 2020. Proc Natl Acad Sci USA. 117(36):22402-22412. 2020. Neurobiol Dis. 140:104867. 2020. Journal of Neurology. 266(11):2743-2751. 2019. Nature Communications. 9(1): 17. 2018. Journal of Experimental Neuroscience. 12:1179069518764892. 2018. Clinical and Experimental Neuroimmunology. 9(4):12474. 2018. J Autoimmun. 88:103-113. 2018. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 3(2): e210. 2016. J Hum Genet. 61(10):899-902. 2016. Heart Vessels. 31(7):1154-61. 2016.