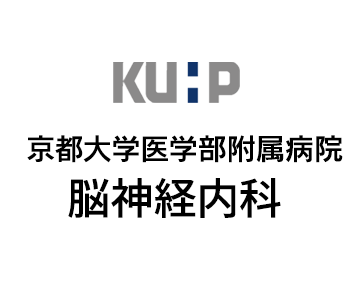ご挨拶

京都大学脳神経内科のホームページにようこそ。
京都大学脳神経内科は1979年(昭和54年)に日本で最初の脳神経内科学の臨床講座として開設された教室です。この度、第四代髙橋良輔教授の後任として2024年10月に教授を拝命いたしました。
京都大学脳神経内科教室は2029年に創立50周年を迎えます。教室の先達が標榜してきた「治る脳神経内科」を私達の代でしっかりと継承し、次の50年に向けて、世界水準の診療・研究・教育を展開し、現在、そして未来の患者さんに最良の医療を提供してまいります。
脳神経内科は、脳神経系の疾患を、内科的知識・技能をもって、専門的に診療する診療科です。「脳の病気」を診るスペシャリストであると同時に、脳から脊髄・末梢神経・筋と、全身に張りめぐらされる神経系の診療を行いますので、「全身」を診ることができる内科のジェネラリストでもあります。脳神経内科が対象とする病気は、パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症に代表される神経難病から、脳卒中・認知症・てんかんといったコモンディジーズまで、そして、脳卒中・脳炎・意識障害などの急性期疾患から、神経難病の在宅診療や神経リハビリ—テーションまで裾野が広く、超高齢社会の本格到来により、脳神経内科医の担う役割は益々増えてきています。
診療面では、基幹大学病院としてあらゆる脳神経疾患の患者さんのニーズに応じるべく、一般外来から専門外来まで、幅広く診療を展開しています。一部の神経・筋の難病では遺伝子治療や核酸医薬による根本治療が始まり、神経免疫疾患に対する生物学的製剤治療が本格化しています。病的なタンパク質が神経細胞に蓄積する神経変性疾患についても、例えばアルツハイマー病のアミロイドタンパクに対する抗体療法などの疾患修飾薬が始まりました。臨床神経科学や治験の成果をいち早く取り入れ、神経難病に対する疾患修飾薬治療の早期導入体制を構築してまいります。京都大学脳神経内科の特徴として、脳神経外科・精神科やiPS細胞研究所(CiRA)との密な連携が挙げられます。診療科横断的なてんかん・パーキンソン病の外科・デバイス治療やCiRA発の最先端治療のシームレスな導入を推進しています。
世界水準の診療には、世界水準の研究がかかせません。21世紀は脳の世紀といわれています。当科のモットーとしてWorld Class Care and Researchを掲げ、脳を「知り」「守り」「治す」ことを臨床神経科学の立場から推進してゆきます。分子生物学・病理学・神経免疫学などの基礎研究からヒトを対象とした神経生理・画像・神経リハビリ—テーション研究までを包括する臨床神経科学の研究拠点をめざします。階層性のある複雑なシステムとして機能し、小宇宙とも例えられる脳の仕組みを理解し、その病気を治すためには、学際的な研究がかかせず、学内・国内外と共同研究を積極的に進めています。
診療と研究の両輪の持続的発展に向けて、臨床神経科学の素養を持ったEffective NeurologistsとPhysician Scientistsの育成に力を入れてまいります。脳神経内科の診断学の醍醐味、すなわち病歴聴取で局在・病因診断から診断の作業仮説を立て、神経診察で仮説を絞り込み、その後の諸検査で検証しながら診断を絞り込むプロセスは、研究面での課題の分析、作業仮説の立案、実験による立証に通じます。カンファレンス・回診を通じて、局在・病因・臨床診断のthree step diagnosisのアートを伝承し、教室スタッフとともに脳神経内科の魅力をしっかりと伝えてゆきます。卒後30年経ってもカンファレンス・回診では新しい発見があり、脳神経内科の魅力は尽きません。脳神経に興味のある学生、初期研修医の皆さん、是非一度病院見学に来て、脳神経内科の魅力に実際に触れてみてください。裾野の広い脳神経内科、やりたいことがきっと見つかります。
四代の教授のもと教室は発展し同門は500名を超えました。教室には活気があり、自由闊達な学風のもと、教室員は個性・多様性を尊重しながら、それぞれに志を立て切磋琢磨しています。診療・教育・研究での人との出会い、繋がりを大切にして、次の50年を見据えた次世代の育成に、教室員とともに一丸となって精一杯努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
令和7年3月吉日
京都大学大学院医学研究科臨床神経学 教授
松本理器